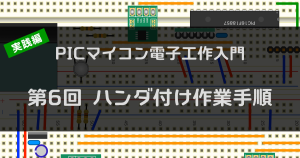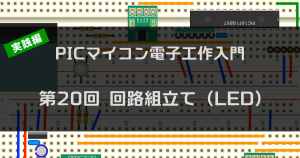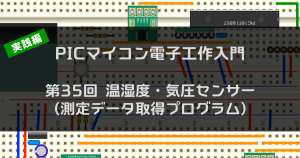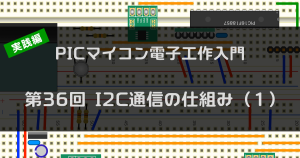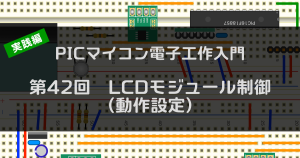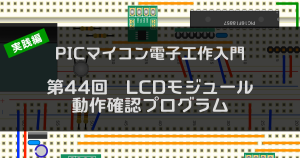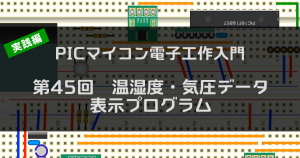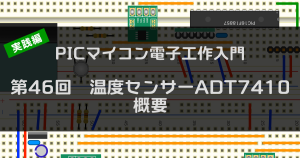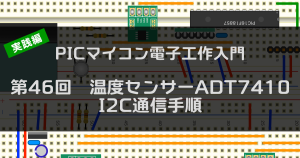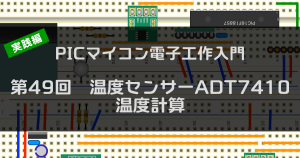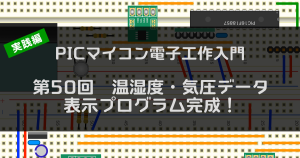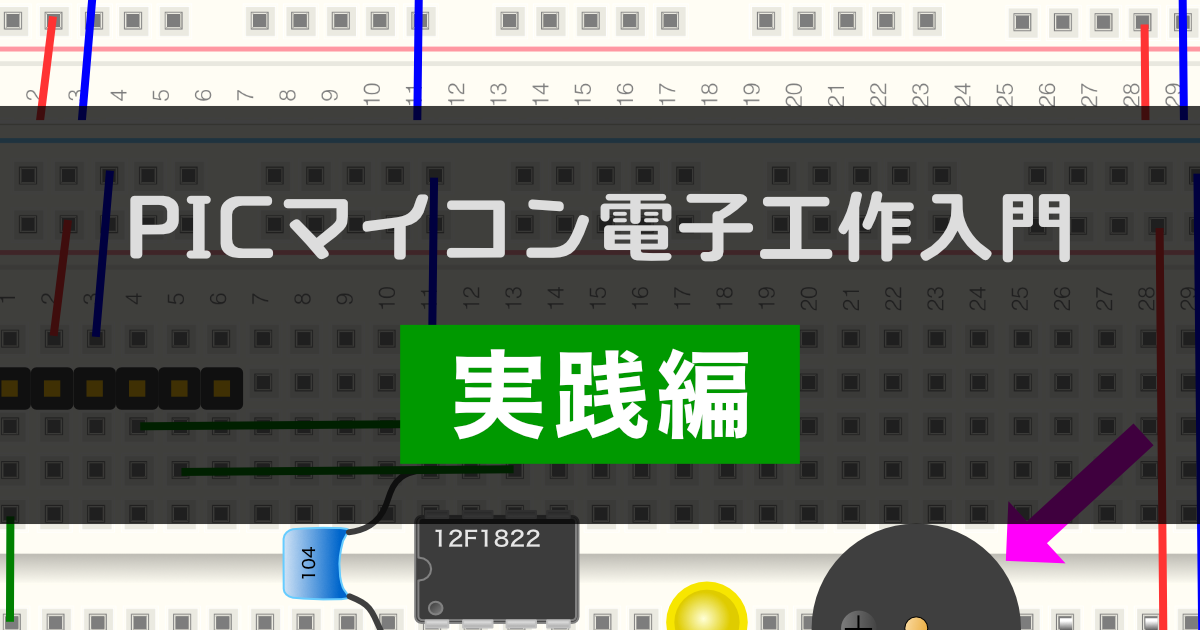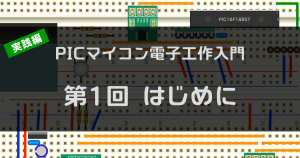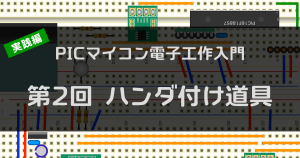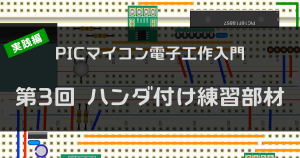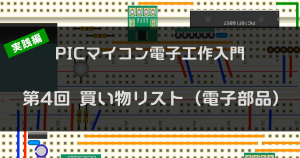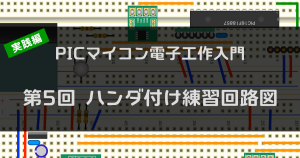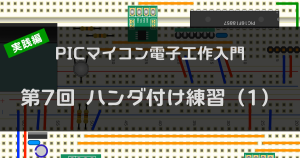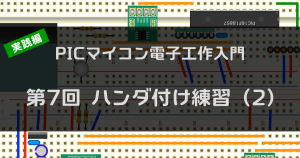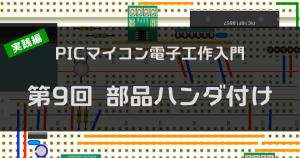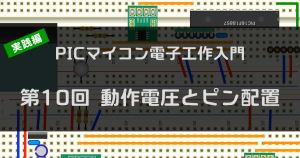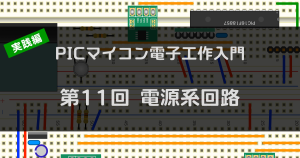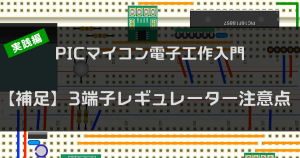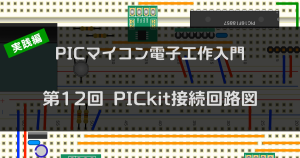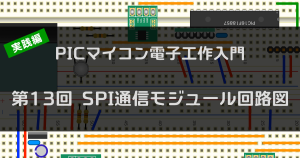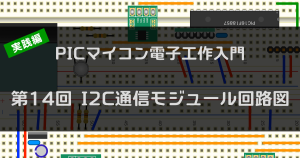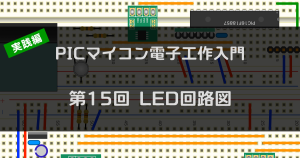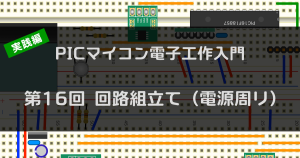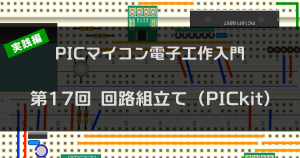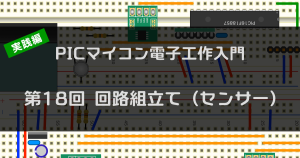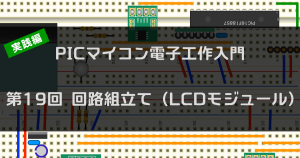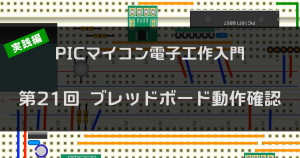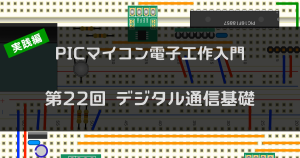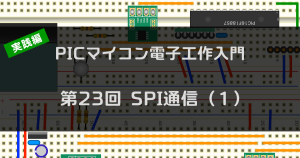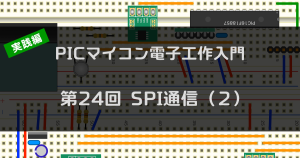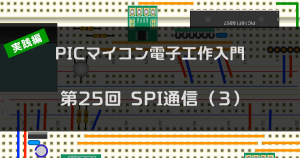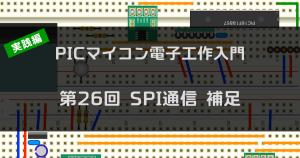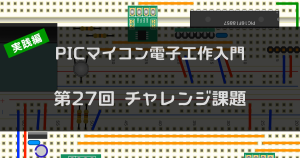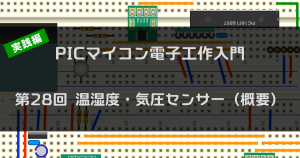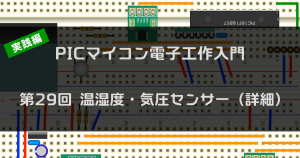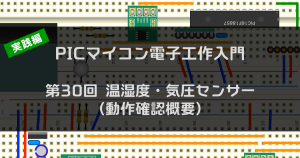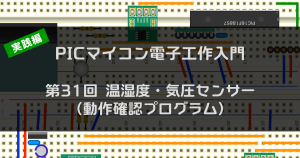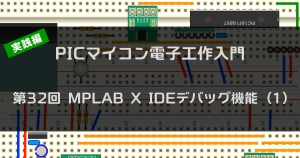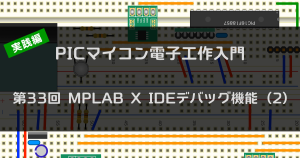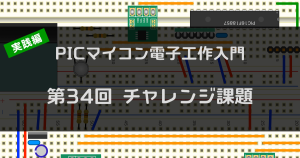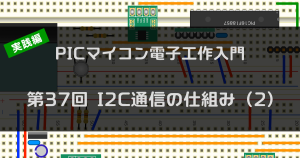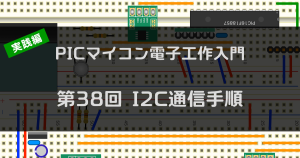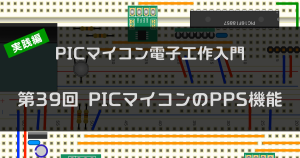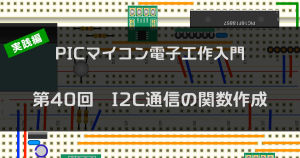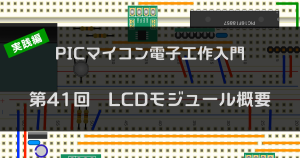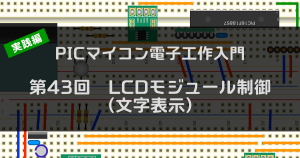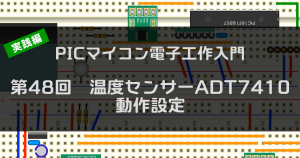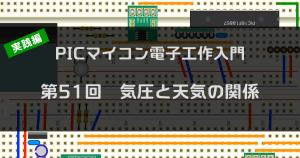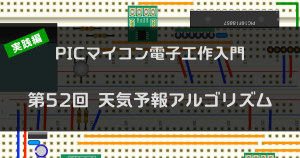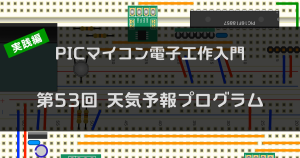PICマイコン電子工作入門の実践編では、センサを使って天気予報システムを製作します。この製作を通してデジタル通信など実践的な内容を習得します。
概要
PICマイコン電子工作入門の【基礎編】と【応用編】では、「PIC12F1822」というマイコンを使用してきましたが、ピン数やメモリ容量に制限があります。
そこで、実践編ではピン数やメモリ容量に余裕のある「PIC16F18857」というPICマイコンを使用して、「天気予報装置」を製作することにより、さらにPICマイコンの機能を習得していきます。
このシリーズでは、PICマイコンがセンサーやLCDモジュールと通信する方法を習得することがメインテーマです。
目次
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第1回 全体像
PICマイコン電子工作入門の基礎編と応用編で触れなかった知識を、実践編としてまとめていきます。第1回目は全体像を説明します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第2回 買い物リスト(ハンダ付け道具)
実践編で必要な道具や電子部品、その他部材のリストを作成します。今回はハンダ付け関連道具についてまとめます。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第3回 買い物リスト(ハンダ付け練習部材)
この記事では、ハンダ付け練習に必要な部材を説明します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第4回 買い物リスト(電子部品・ツール)
今回は、電子部品の買い物リスト作成と、ツールの確認をします。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第5回 ハンダ付け練習の回路図
ハンダ付け練習用の回路図を説明します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第6回 ハンダ付け作業手順
今回は、ハンダ付け作業の手順とコツを確認します。 今回の説明内容 実際にハンダ付けを行う前に、ハンダ付けの手順やコツを説明します。 ハンダ付けは、ハンダを溶かし…
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第7回 ハンダ付け練習(1)
今回は練習基板で実際にハンダ付けを行います。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第8回 ハンダ付け練習(2)
ハンダ付け練習基板にもう1個LEDを追加します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第9回 部品ハンダ付け
ハンダ付け手順を確認しましたので、いよいよセンサと液晶ディスプレイモジュールのハンダ付けを行います!
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第10回 動作電圧とPIC16F18857ピン配置の確認
今回から回路図を作成していきます。最初は使用する部品について確認します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
【補足】 3端子レギュレーターの注意点
今回は3端子レギュレーターを使用する上での注意点を説明します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第12回 PICkitコネクタ接続回路図
PICkitとPICマイコンの接続部分の回路図を作成します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第13回 SPI通信モジュール回路図
今回はSPIセンサモジュールの回路図を作成します。(同じ名前の端子同士を接続するだけです…)
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第14回 I2C通信モジュール回路図
今回は、I2C通信を行う温度センサーとLCDモジュールの回路図を作成します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第15回 LED回路図
最後にLEDを接続します。これで回路図の作成は完了です!
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第16回 ブレッドボード回路組立て(電源周り)
今回からブレッドボードに回路を組み立てていきます。最初は電源周りです。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第17回 ブレッドボード回路組立て(PICkit部分)
今回はPICKitとPICマイコンの接続回路部分を組み立てます。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第18回 ブレッドボード回路組立て(温湿度気圧センサー)
今回はPICマイコンの電源接続と温湿度・気圧センサの回路を組立てます。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第20回 ブレッドボード組み立て 〜LED回路〜
LED回路を組み立てて、ブレッドボードを完成させます。 回路図 今回使用する2色LEDは、次のようにRB0ピンとRB1ピンに接続します。 ブレッドボードを組み立てる前に、2色…
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第21回 ブレッドボードの動作確認
今回はブレッドボードの回路が正しく動作するか確認します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第22回 デジタル通信の基礎
I2C通信やSPI通信の説明に入る前に、マイコンで通信を行うにはどうすればよいのか、基礎的な概念を解説します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第23回 SPI通信(1)
今回からSPI通信の仕組みを理解していきます。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第24回 SPI通信(2)
データ通信システムを拡張して、実際のSPI通信の仕様に近い形にしていきます。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第25回 SPI通信(3)
今回のデータ通信システムの検討で、SPI通信の基本形が完成します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第26回 SPI通信 補足
今回の記事では、実際のSPI通信手順の補足説明をします。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第27回 チャレンジ課題
データ通信手順に関して、チャレンジ課題に挑戦してみます。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第28回 温湿度・気圧センサー(概要)
BME280温湿度・気圧センサーの仕様の概要を確認します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第29回 温湿度・気圧センサー(詳細)
今回は温湿度・気圧センサーモジュールの詳細仕様を説明します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第30回 温湿度・気圧センサー(動作確認概要)
温湿度・気圧センサーから測定データを取得する前に、簡単なプログラムを作成してSPI通信できるか確認します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第31回 温湿度・気圧センサー(動作確認プログラム)
今回は、センサーモジュールのIDを取得するプログラムを作成します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第32回 MPLAB X IDEデバッグ機能(1)
前回作成したプログラムの動作確認と、MPLAB X IDEのデバッグ機能の使い方を確認します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第33回 MPLAB X IDEデバッグ機能(2)
今回はMPLAB X IDEの主なデバッグ機能を確認します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第34回 チャレンジ課題
SPI通信とデバッグ機能のチャレンジ課題に挑戦してみます!
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第35回 温湿度・気圧センサー(測定データ取得プログラム)
温湿度・気圧センサーBME280のデータシートを参考にして、温湿度・気圧データの取得プログラムを作成します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第36回 I2C通信の仕組み(1)
今回からI2C通信手順の説明に入ります。 SPI通信の特徴確認 I2C通信手順の説明に入る前に、SPI通信を振り返っておきましょう。 SPI通信を行うには、ホストとデバイスを…
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第37回 I2C通信の仕組み(2)
I2C通信のハードウェアと通信手順の概略を説明します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第38回 I2C通信手順
前回までの記事内容をベースにして、I2C通信手順を説明します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第39回 PICマイコンのPPS機能
I2C通信プログラムを作成する前に、PICマイコンの「PPS機能」の使い方を説明します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第40回 I2C通信の関数作成
今回から、PICマイコンのI2C通信のプログラム作成に入ります。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第41回 LCDモジュール概要
今回からLCDモジュールをI2C通信で制御するプログラムを作成していきます。最初はLCDモジュールの概要説明です。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第42回 LCDモジュール制御(動作設定)
今回は液晶モジュール(AQM1602XA / ST7032)の制御方法の説明です。 AQM1602XAで表示できる文字 実践編で使用するLCDモジュール(AQM1602XA)はキャラクタディスプレイ…
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第43回 LCDモジュール制御(文字表示)
今回の記事では、LCDディスプレイに文字を表示するコマンドを説明します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第44回 LCDモジュール動作確認プログラム
LCDモジュールの制御方法がわかりましたので、今回は動作確認を目的として文字列を表示する簡単なプログラムを作成します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第45回 BME280温湿度・気圧データ表示プログラム
LCDモジュールの制御方法を確認しましたので、BME280で取得した温湿度・気圧データをLCDモジュールに表示するプログラムを作成します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第46回 温度センサーADT7410(概要)
今回の記事から、温度センサーADT7410から温度データを取得するプログラムを作成します。今回はセンサの概要説明です。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第47回 温度センサーADT7410(I2C通信手順)
温度センサー(ADT7410)のI2C通信では、LCDモジュールとは違った通信手順が必要です。今回の記事では、その通信手順を説明します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第48回 温度センサーADT7410(動作設定)
今回の記事では温度センサー(ADT7410)の動作設定方法を説明します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第49回 温度センサーADT7410(温度計算)
温度センサーから取得したデータから、温度を求める方法を説明します。 温度センサADT7410の温度データ ADT7410で測定した温度は、メモリマップのアドレス0x00と0x01に…
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第50回 温湿度・気圧データ表示プログラム
今回の記事では、温湿度と気圧データをLCDモジュールに表示するプログラムを完成します。湿度と気圧データはBME280から取得、温度データはADT7410から取得します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第51回 気圧と天気の関係
今回製作したブレッドボードで天気予報をしてみたいと思います。最初に天気と気圧の関係を調べてみます。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第52回 天気予報アルゴリズム
今回は天気予報のアルゴリズムを検討します。
PICマイコン電子工作入門 〜実践編〜
第53回 天気予報プログラム(最終回)
天気予報のアルゴリズムをプログラムに実装します。