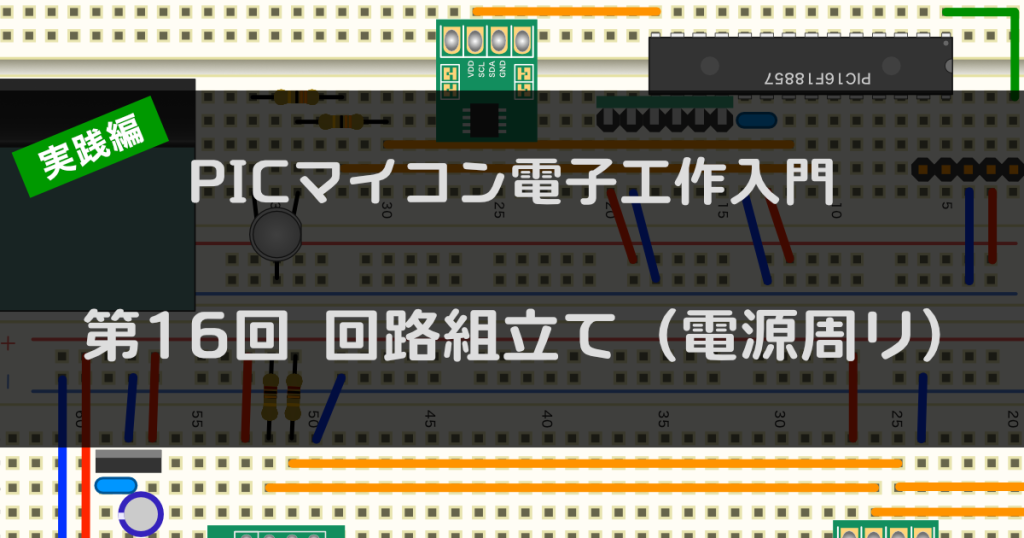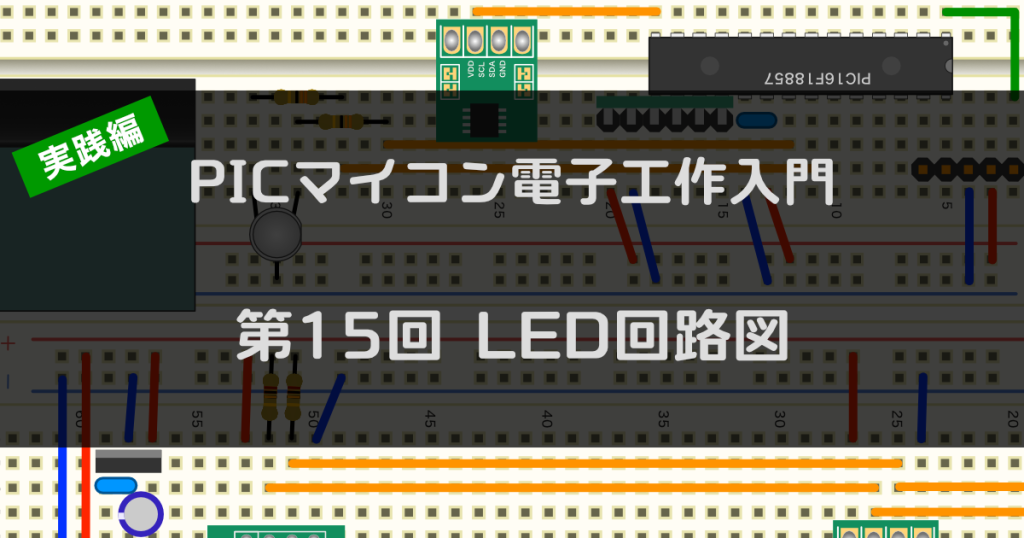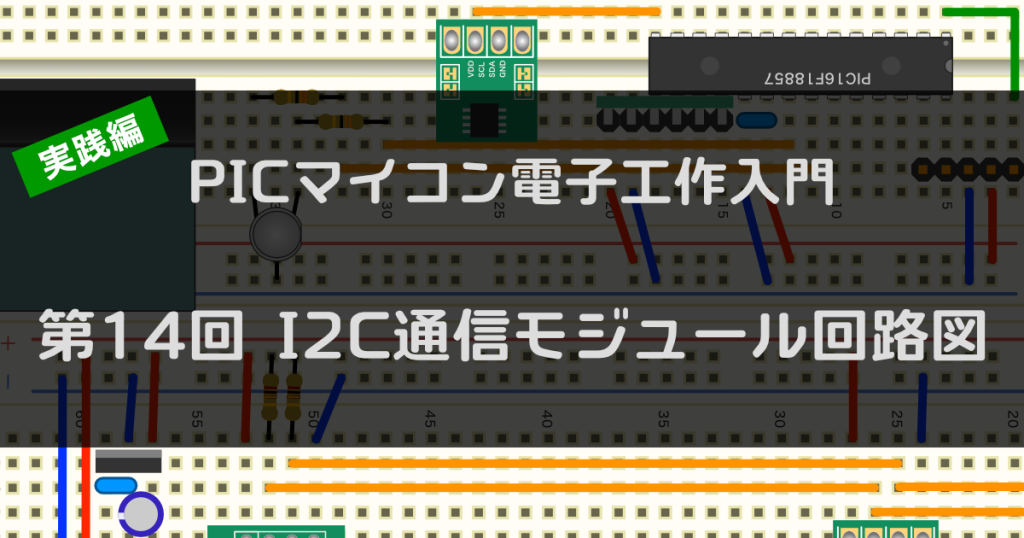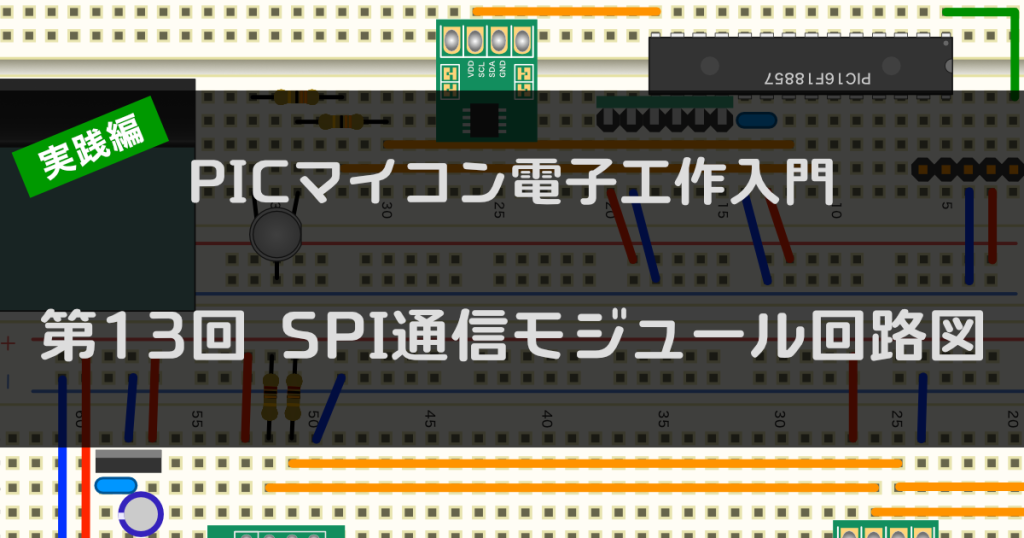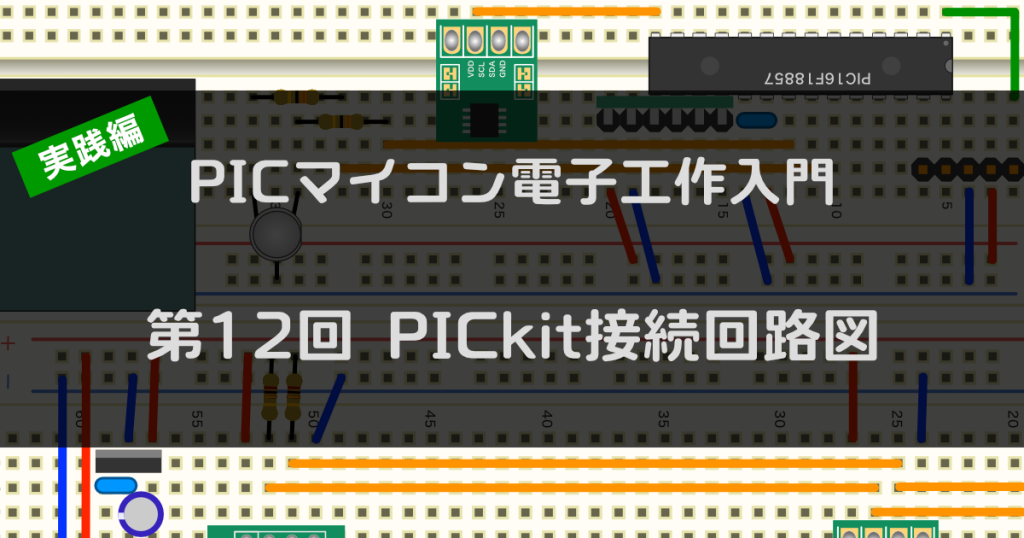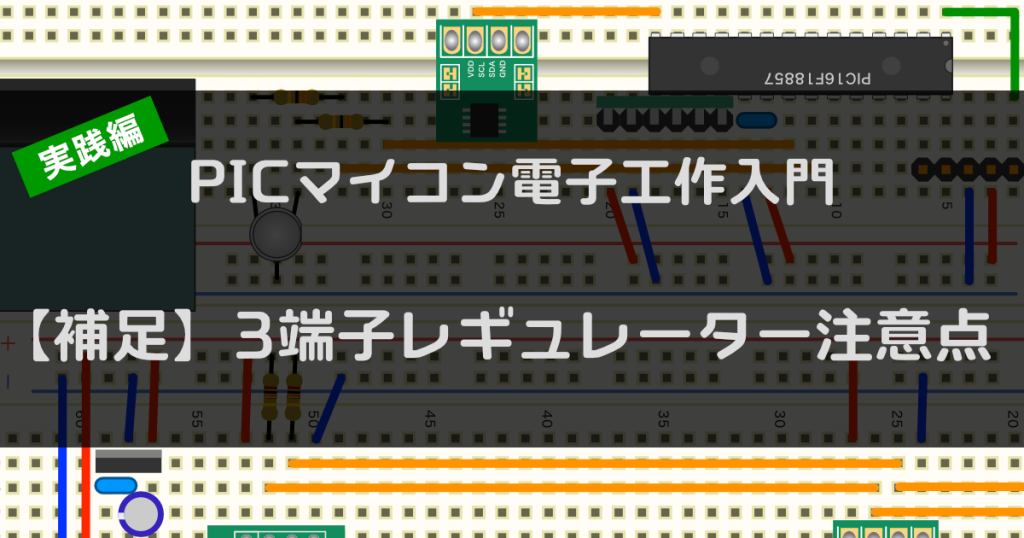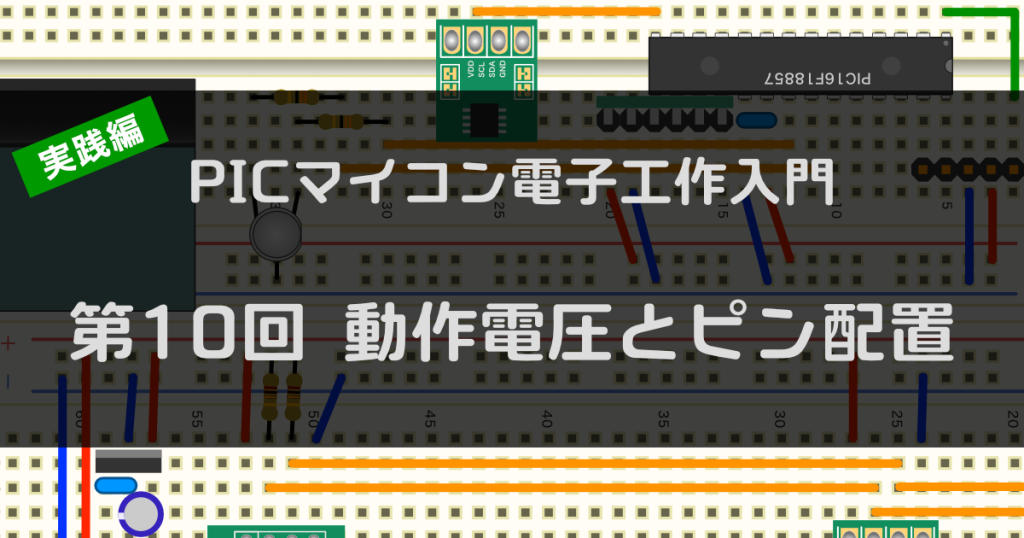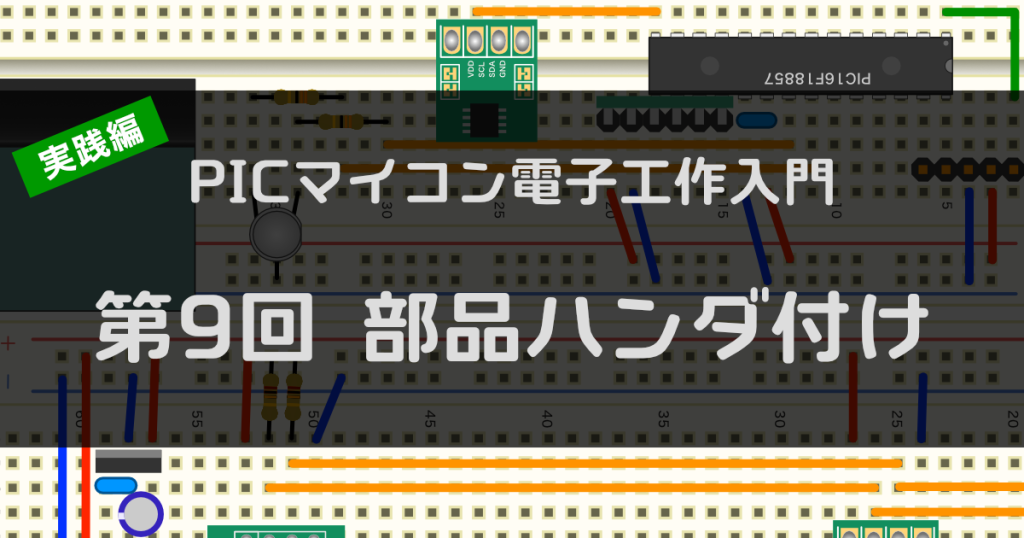PICマイコン入門(実践)– category –
-

第16回 ブレッドボード回路組立て(電源周り)
今回からブレッドボードに回路を組み立てていきます。最初は電源周りです。 -

第15回 LED回路図
最後にLEDを接続します。これで回路図の作成は完了です! -

第14回 I2C通信モジュール回路図
今回は、I2C通信を行う温度センサーとLCDモジュールの回路図を作成します。 -

第13回 SPI通信モジュール回路図
今回はSPIセンサモジュールの回路図を作成します。(同じ名前の端子同士を接続するだけです...) -

第12回 PICkitコネクタ接続回路図
PICkitとPICマイコンの接続部分の回路図を作成します。 -

【補足】 3端子レギュレーターの注意点
今回は3端子レギュレーターを使用する上での注意点を説明します。 -

第11回 回路図設計 〜電源系回路〜
今回は電源関連の回路の作成です。 -

第10回 動作電圧とPIC16F18857ピン配置の確認
今回から回路図を作成していきます。最初は使用する部品について確認します。 -

第9回 部品ハンダ付け
ハンダ付け手順を確認しましたので、いよいよセンサと液晶ディスプレイモジュールのハンダ付けを行います!