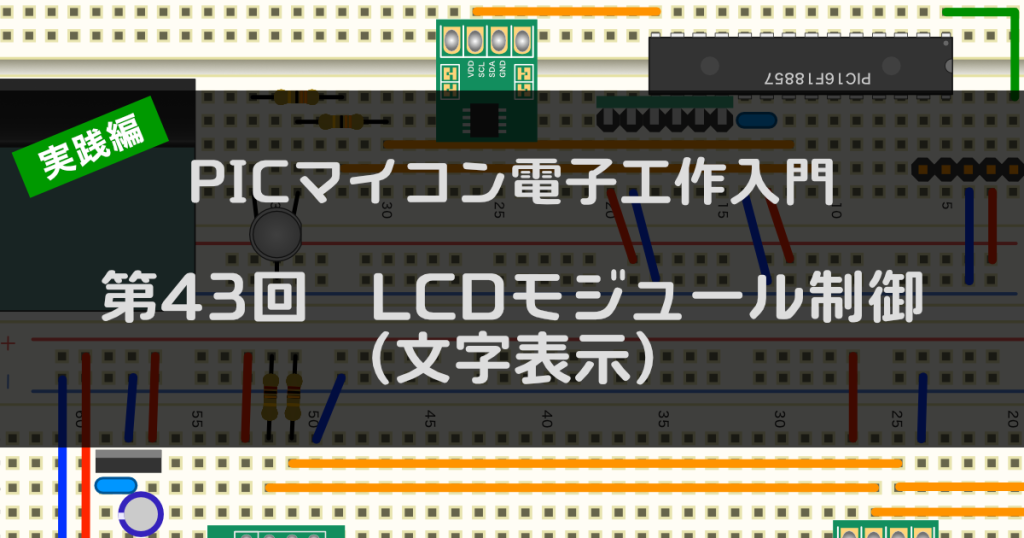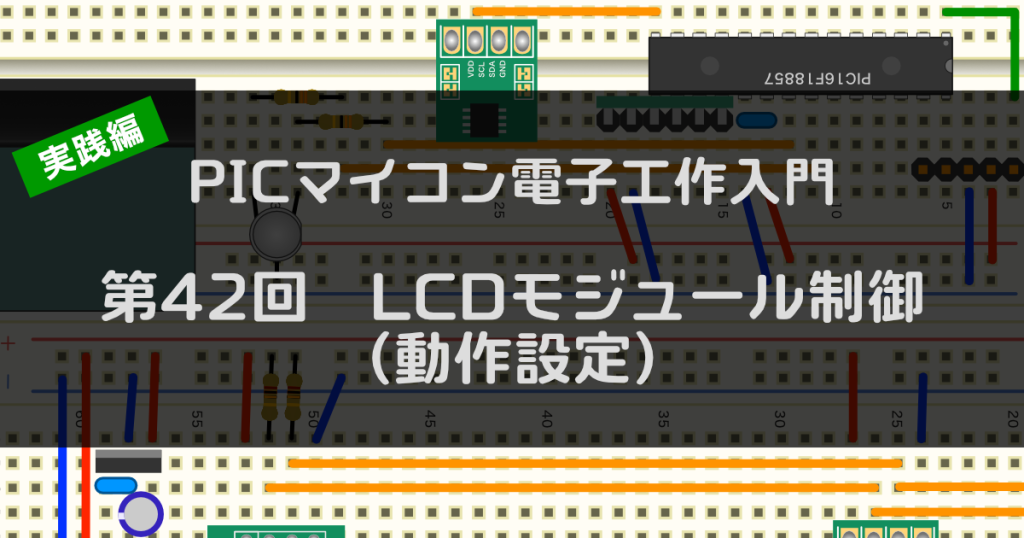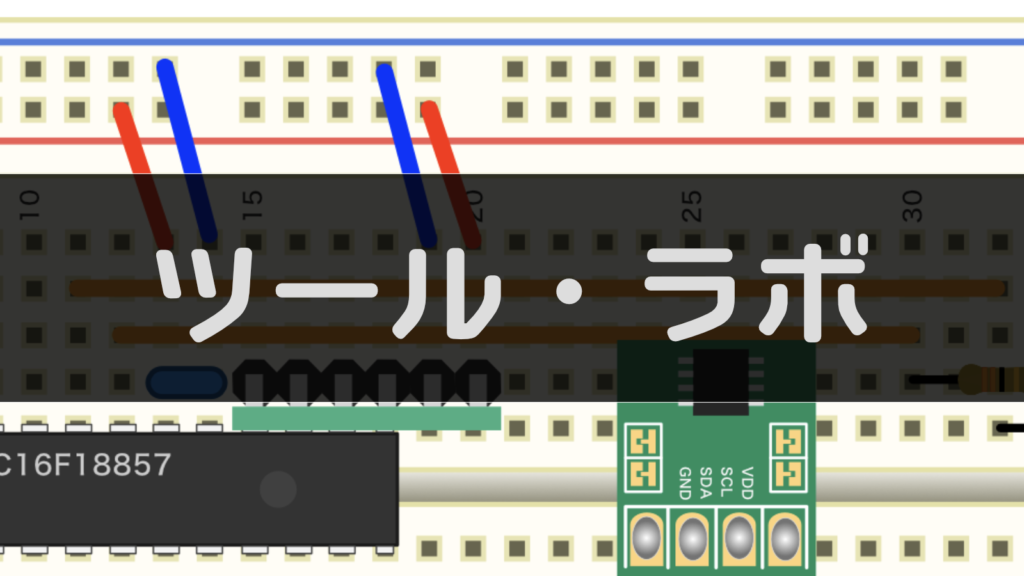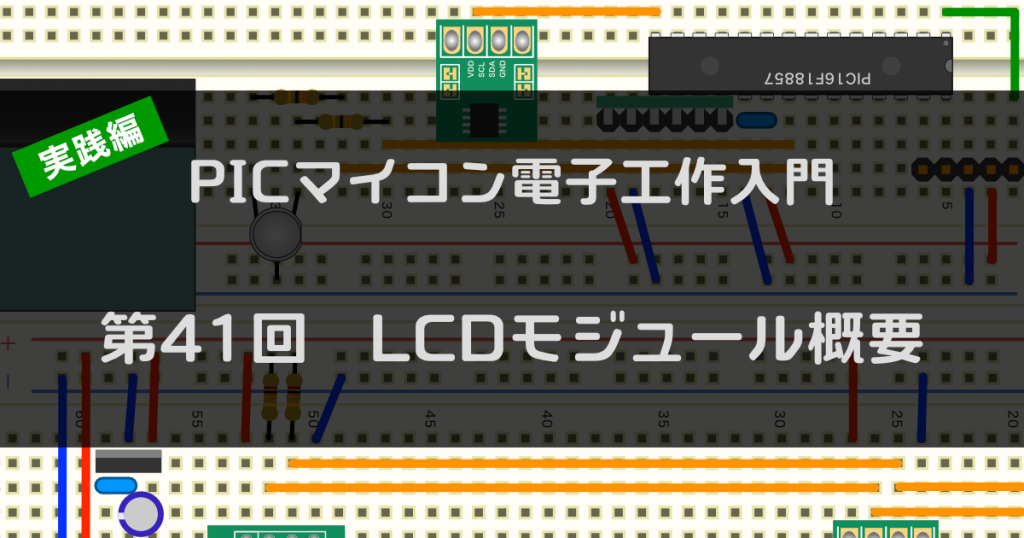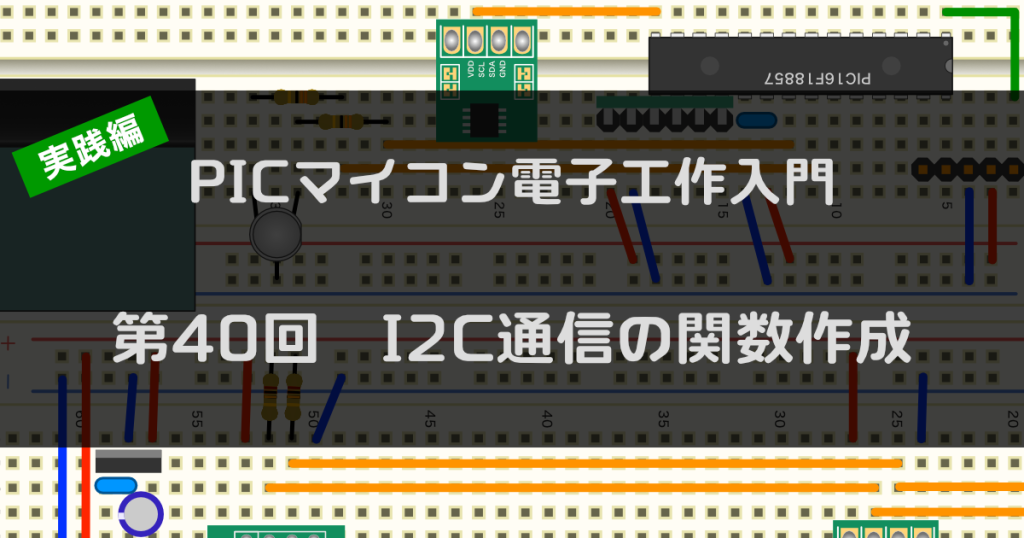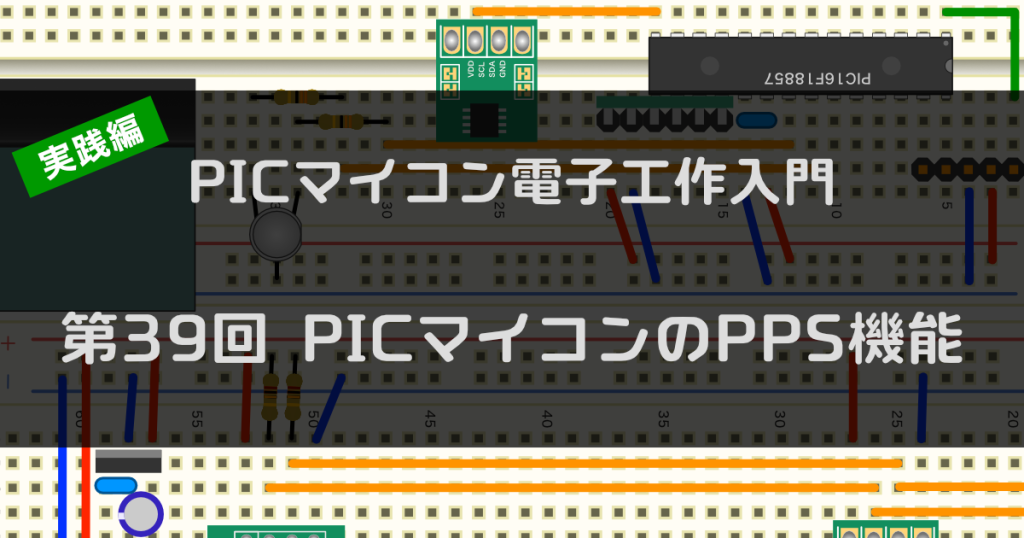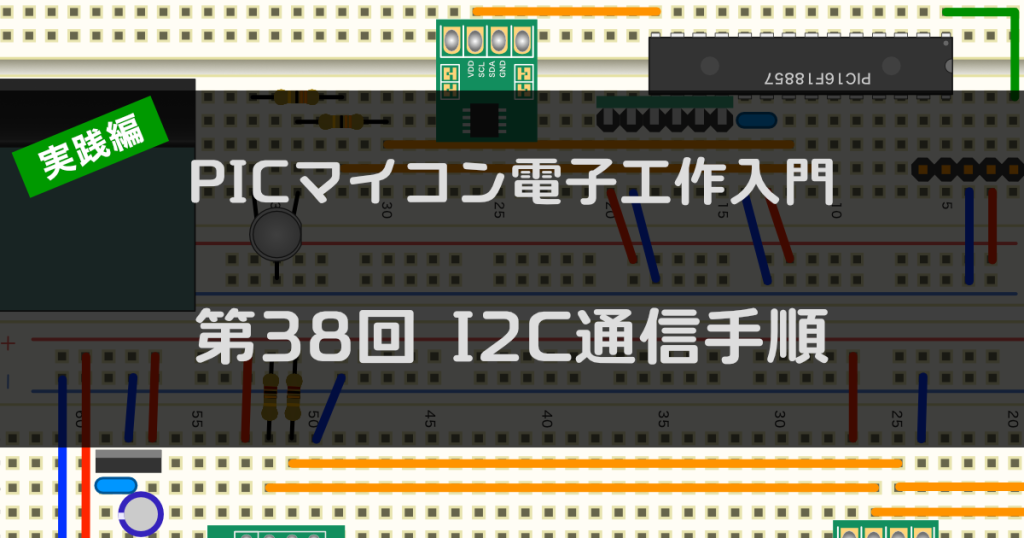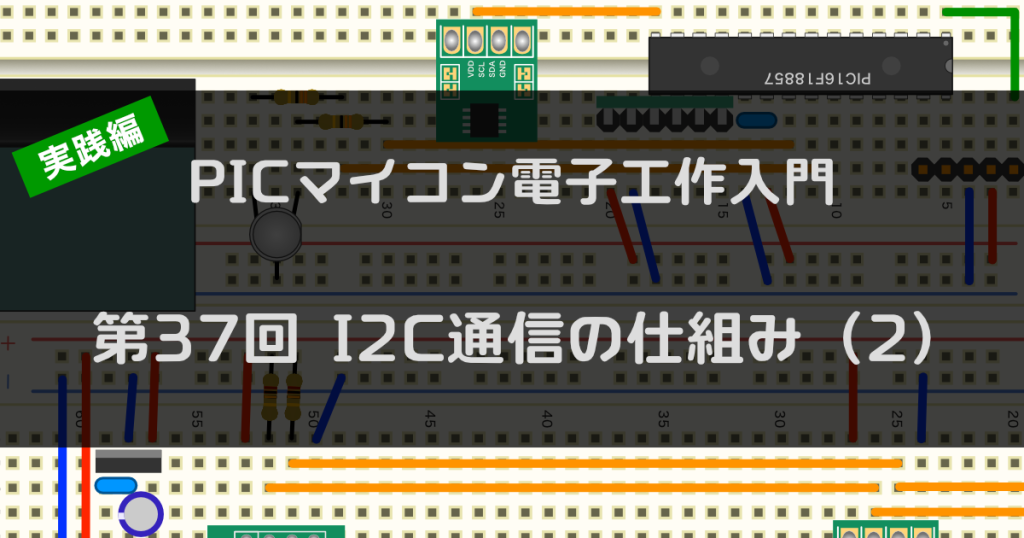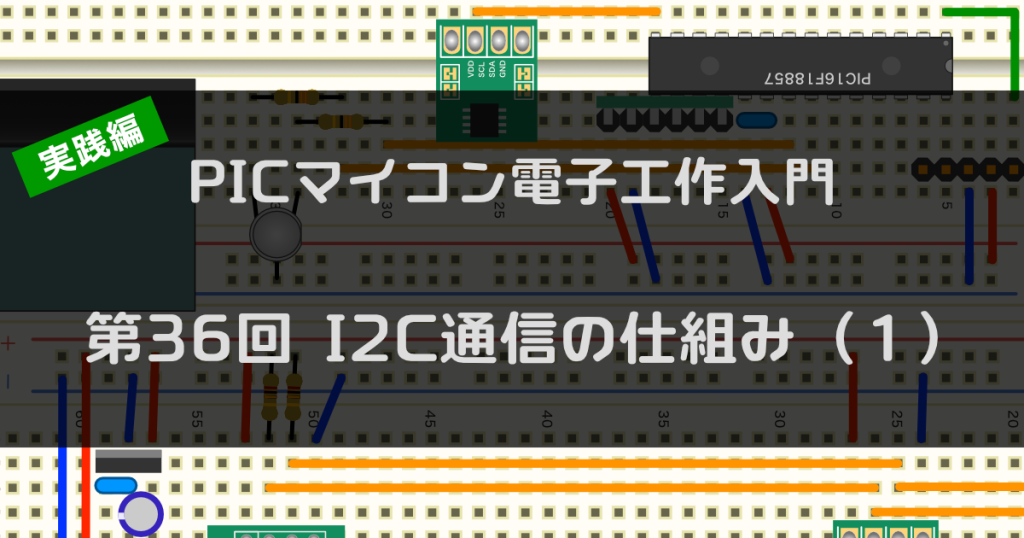入門シリーズ– category –
入門シリーズのトップリンクページ
-

第43回 LCDモジュール制御(文字表示)
今回の記事では、LCDディスプレイに文字を表示するコマンドを説明します。 -

第42回 LCDモジュール制御(動作設定)
今回は液晶モジュール(AQM1602XA / ST7032)の制御方法の説明です。 AQM1602XAで表示できる文字 実践編で使用するLCDモジュール(AQM1602XA)はキャラクタディスプレイです。 そこで、最初にこの液晶モジュールで表示できる文字の種類を確認しておきます。 次の表はAQM1602XAのデータシートに記載さている、表示できる文字種です。 表示する... -

第14回補足 Raspberry Piの名前を変更する
Raspberry Piを接続するのに「raspberrypi.local」という名前で接続していますが、複数台ある場合は名前では区別できません。どうすればよいのでしょうか。 Raspberry Piを複数台接続する 今までの説明で、リモートで接続する場合、 ssh pi@raspberrypi.local と入力して接続していました。 この記事を書く際、検証用として同じネットワーク... -

第41回 LCDモジュール概要
今回からLCDモジュールをI2C通信で制御するプログラムを作成していきます。最初はLCDモジュールの概要説明です。 -

第40回 I2C通信の関数作成
今回から、PICマイコンのI2C通信のプログラム作成に入ります。 -

第39回 PICマイコンのPPS機能
I2C通信プログラムを作成する前に、PICマイコンの「PPS機能」の使い方を説明します。 -

第38回 I2C通信手順
前回までの記事内容をベースにして、I2C通信手順を説明します。 -

第37回 I2C通信の仕組み(2)
I2C通信のハードウェアと通信手順の概略を説明します。 -

第36回 I2C通信の仕組み(1)
今回からI2C通信手順の説明に入ります。 SPI通信の特徴確認 I2C通信手順の説明に入る前に、SPI通信を振り返っておきましょう。 SPI通信を行うには、ホストとデバイスを次のような信号線で接続しました。 データ送受信のタイミング(=データ信号の読み取りタイミング)は、ホストのクロック信号(SCK)が司っています。 ホストからデバイスに...