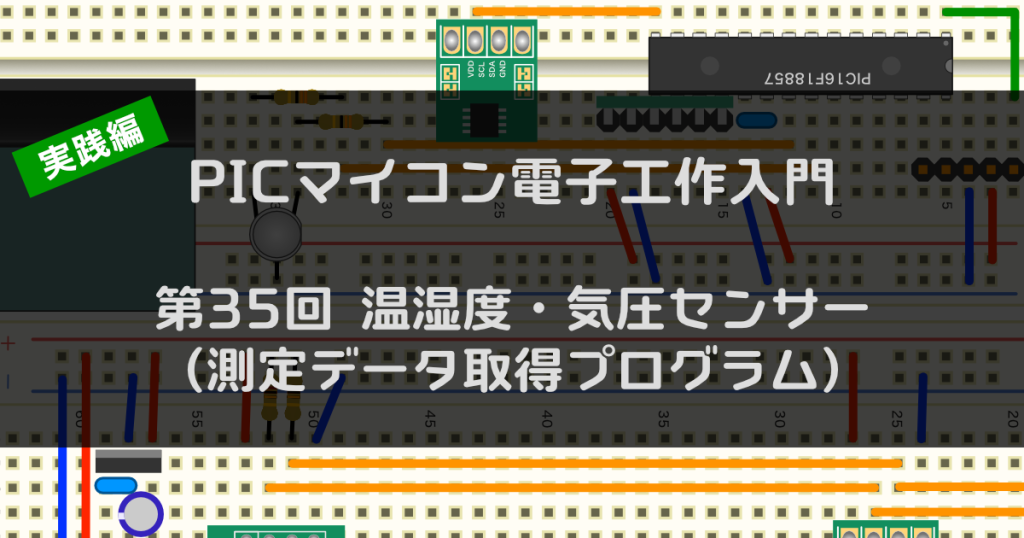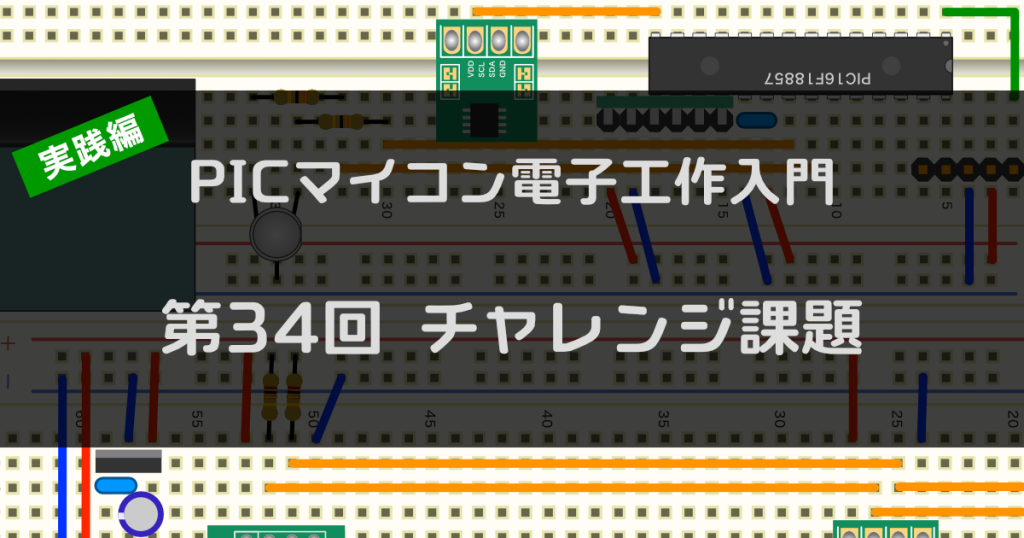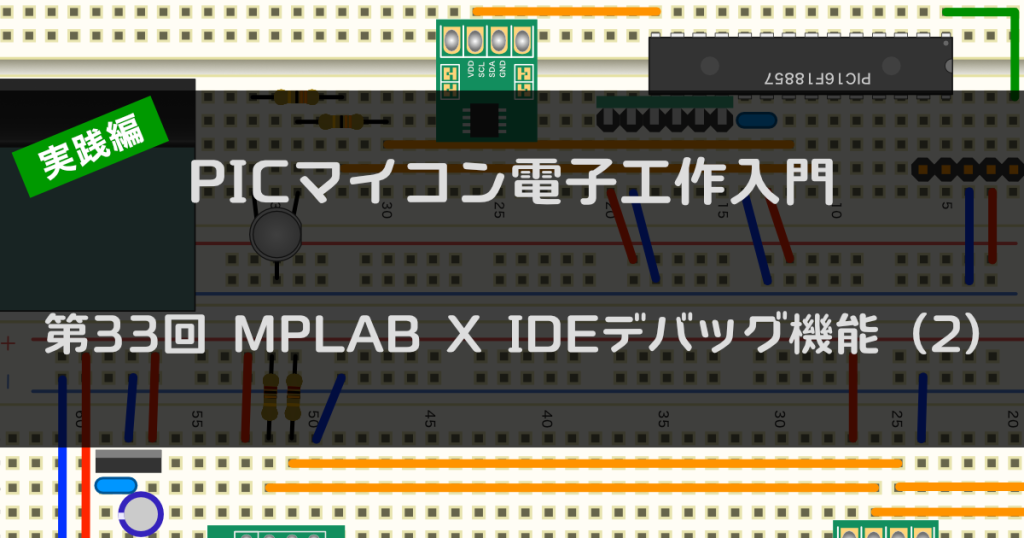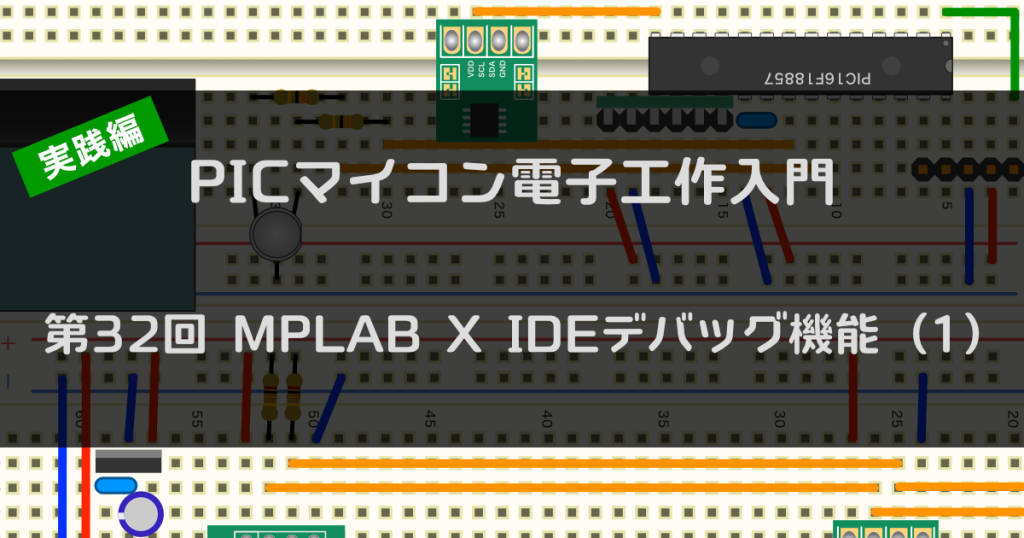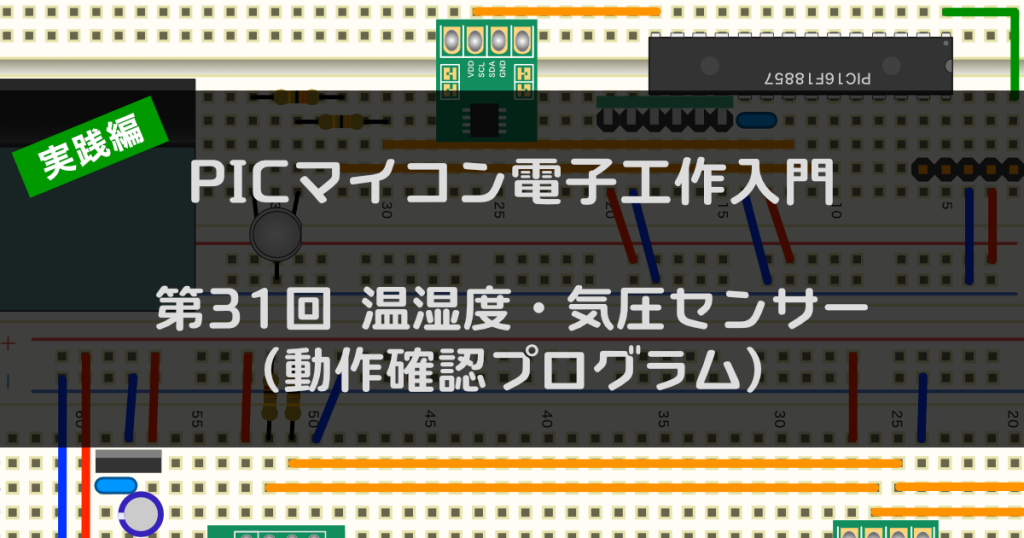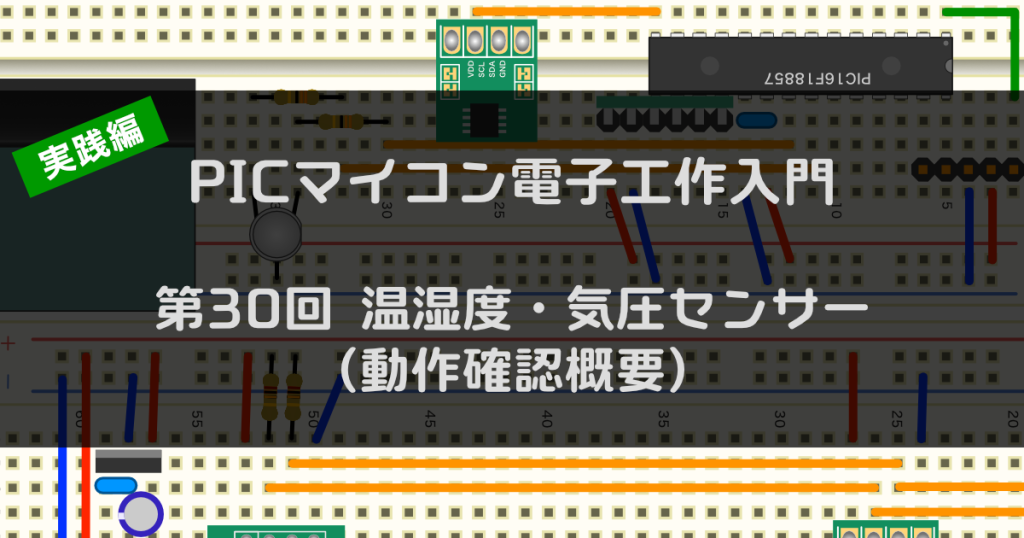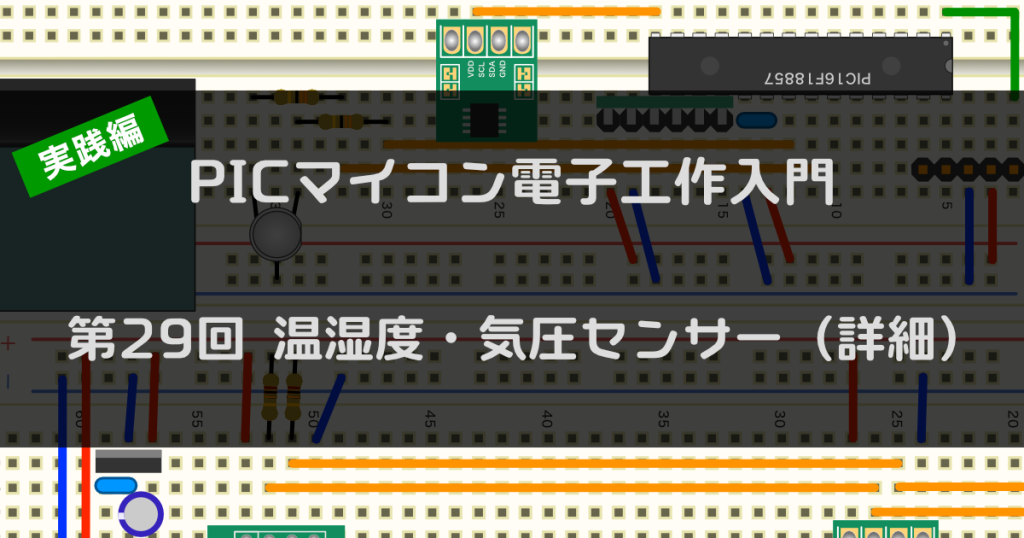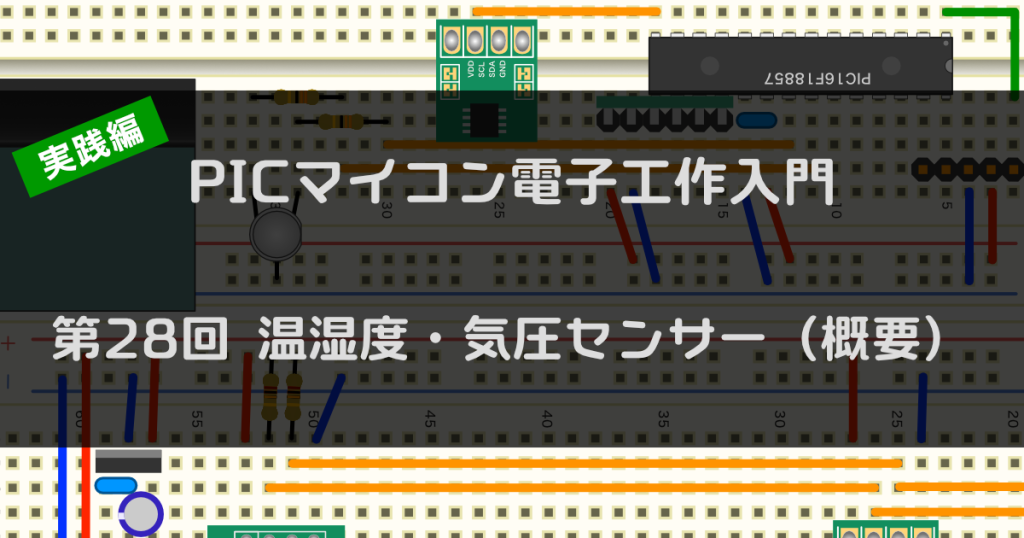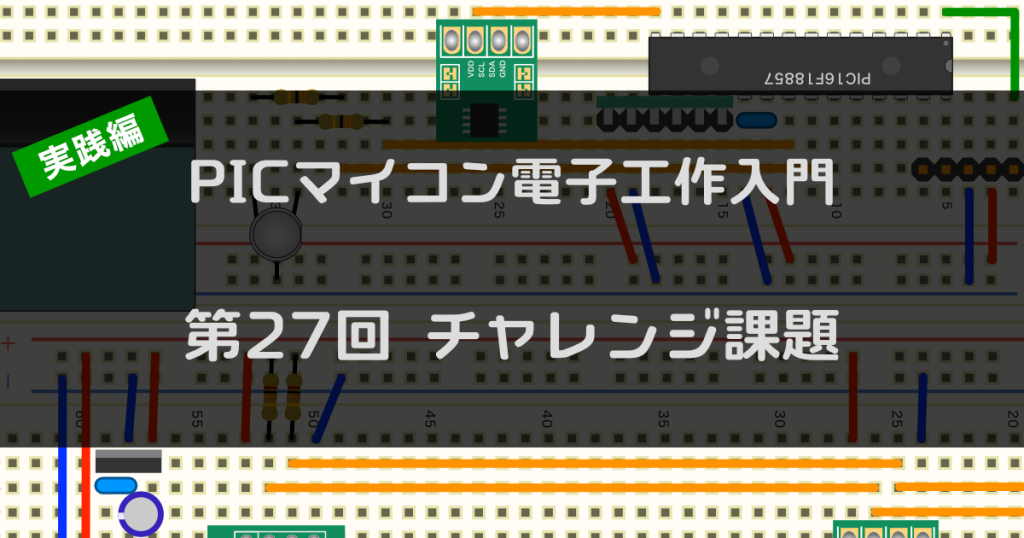PICマイコン入門(実践)– category –
-

第35回 温湿度・気圧センサー(測定データ取得プログラム)
温湿度・気圧センサーBME280のデータシートを参考にして、温湿度・気圧データの取得プログラムを作成します。 -

第34回 チャレンジ課題
SPI通信とデバッグ機能のチャレンジ課題に挑戦してみます! -

第33回 MPLAB X IDEデバッグ機能(2)
今回はMPLAB X IDEの主なデバッグ機能を確認します。 -

第32回 MPLAB X IDEデバッグ機能(1)
前回作成したプログラムの動作確認と、MPLAB X IDEのデバッグ機能の使い方を確認します。 -

第31回 温湿度・気圧センサー(動作確認プログラム)
今回は、センサーモジュールのIDを取得するプログラムを作成します。 -

第30回 温湿度・気圧センサー(動作確認概要)
温湿度・気圧センサーから測定データを取得する前に、簡単なプログラムを作成してSPI通信できるか確認します。 -

第29回 温湿度・気圧センサー(詳細)
今回は温湿度・気圧センサーモジュールの詳細仕様を説明します。 -

第28回 温湿度・気圧センサー(概要)
BME280温湿度・気圧センサーの仕様の概要を確認します。 -

第27回 チャレンジ課題
データ通信手順に関して、チャレンジ課題に挑戦してみます。